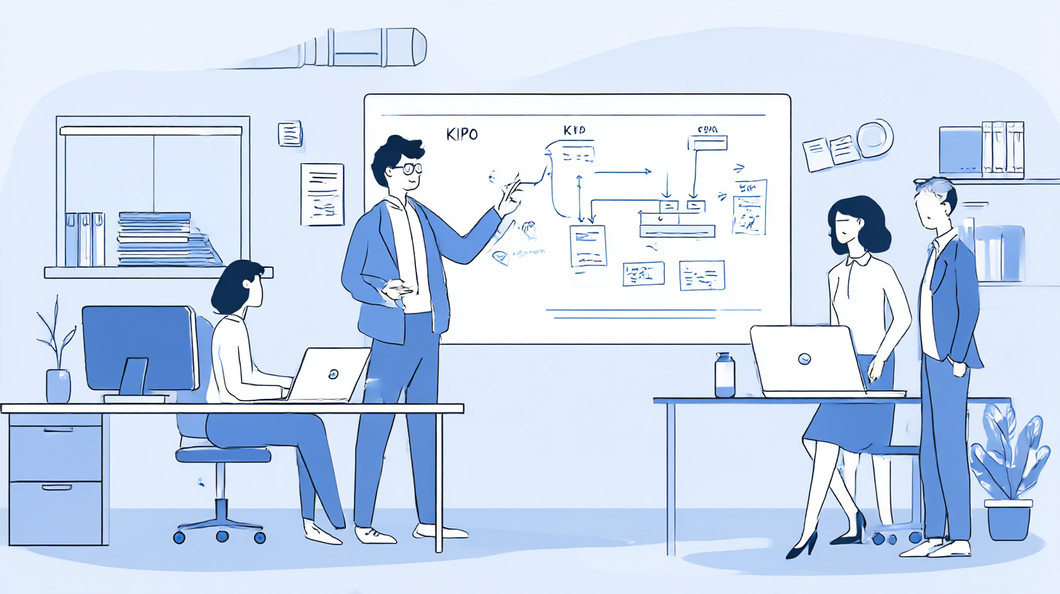IT業界のインサイドセールスとは?
インサイドセールスは、アポイントを取って訪問する営業とは異なり、見込み客を対象に非対面で行う営業活動です。具体的なコミュニケーション手段として、電話、メール、Web会議システムなどが挙げられます。インサイドセールスは、その特徴から内勤営業やリモートセールスとも呼ばれます。具体的に、どのような営業活動なのでしょうか。
必要性
IT業界においても、インサイドセールスの必要性は、年々、高まっています。主な理由として以下の点が挙げられます。 【必要性が高まっている理由】
- 人員不足に対応するため
- 営業担当者の負担を軽減するため
内勤で複数の見込み客とコミュニケーションを図れるため、人員不足対策や働き方改革の一環としてインサイドセールスを導入するケースが少なくありません。また、海外など、遠隔地の見込み客に対して営業活動を行うため、インサイドセールスを導入することもあります。今後は、その必要性がさらに高まると予想されます。
仕事の内容
インサイドセールスの主な仕事は、マーケティング部門が獲得した見込み客を育成して、受注確度が高い見込み客として営業部門に引き渡すことです。簡単に説明すると、見込み客が抱えている課題を明らかにし、解決策として自社の製品やサービスを検討してもらう、あるいは利用してもらう状態にすることといえるでしょう。 具体的には、ステップメールの配信、ホワイトペーパーの提供、要望のヒアリング、受注確度に基づく見込み客の分類などを行います。また、見込み客のニーズを的確にとらえて、適切な部門に引き継ぐこともインサイドセールスの仕事です。見込み客の状態によっては、営業部門ではなくマーケティング部門に引き継ぐ場合もあります。営業代行でも人気の業務となっています。
メリット・デメリット
インサイドセールスの導入により得られる代表的なメリットは以下の3点です。 【メリット】
- 営業活動の効率化を図れる
- 距離を問わず営業活動を行える
- コストを削減しやすくなる
インサイドセールスを導入すると、1日でアプローチできる見込み客の数、1人の担当者がアプローチできる見込み客の数を増やせます。非対面で営業活動を行えるうえ、同時に複数の見込み客を担当できるためです。営業代行サービスでは欠かせません。距離を問わず営業活動を行えるようになる点も見逃せません。非対面で営業活動を行うため、遠隔地や海外の見込み客にも対応できるようになります。営業範囲を拡大できるケースが多いでしょう。 これらの理由から、コスト削減を目指せます。営業活動の効率を高められるうえ、交通費や移動時間も抑えられるためです。 インサイドセールスの導入には、気をつけたいデメリットもあります。具体的には、適切に運用できる組織体制を整えることが求められます。マーケティング部門、インサイドセールス部門、営業部門の連携が不十分だと、情報を共有・管理できないため狙った効果を発揮できない恐れがあります。また、非対面で営業活動を行うため、見込み客から信頼を獲得しにくい点にも注意が必要です。これらの課題を踏まえたうえで、慎重に導入を進める必要があります。
フィールドセールスとの違い
フィールドセールスは、外勤営業を指します。見込み客のもとを訪れて、商談を行う従来型の営業活動といえるでしょう。インサイドセールスとフィールドセールスは、役割が異なります。両者の基本的な役割は以下の通りです。 営業手法 役割 インサイドセールス 見込み客の育成 フィールドセールス 契約の締結 時間をかけて非対面でコミュニケーションを図れるインサイドセールスは見込み客の育成、対面で信頼関係を構築できるフィールドセールスは案件の受注に適しています。したがって、両者を組み合わせて営業活動を行うことが一般的です。
IT業界におけるインサイドセールスのポイント
 続いて、IT業界におけるインサイドセールスのポイントを解説します。
続いて、IT業界におけるインサイドセールスのポイントを解説します。
マーケティング戦略への位置づけ
インサイドセールスは、マーケティングで収集した顧客情報を活用します。そのため、マーケティング戦略にインサイドセールスを位置づけ、両者の連携を強化しておくことが重要です。具体的な取り組みとして、共通の目標を設定する、情報を共有しやすい体制を構築しておくなどが考えられます。
ターゲットの選定
ターゲットの選定やターゲットの理解も、インサイドセールスの成否にかかわります。それぞれにあわせた方法で、アプローチする必要があるためです。個別性を無視すると、商談の機会を効率よく創出できません。ターゲットの課題やニーズを把握してターゲットに訴求しやすい方法でアプローチすることが求められます。インサイドセールスを計画的に展開することが重要です。
PDCAサイクルの展開
PDCAサイクルを展開すると、インサイドセールスの目標を達成しやすくなります。ポイントは、フィールドセールスと連動したKPIを設定することです。具体的なKPIの例として以下のものが挙げられます。 項目 内容 アクション数 電話、メールなど、具体的な行動を起こした件数 有効会話数 見込み客の担当者と電話がつながりヒアリングできた件数 商談化数 商談につながった件数 有効商談数 受注につながる可能性が高い商談の件数 受注数 受注につながった商談の件数 採用するKPIと数値目標は、自社のKGIなどをもとに設定します。PDCAを展開する中で、必要があればKPIを見直すことも重要です。
デジタルツール・システムの導入
インサイドセールスの主な役割は、マーケティング部門と営業部門の橋渡しをすることです。したがって、両部門との情報共有が欠かせません。CRMツールやSFAツールなどのデジタルツール・システムを導入すると、情報共有を図りやすくなります。また、見込み客の状態にあわせてメールを自動配信するなど、業務の効率化も目指せます。インサイドセールスの質を高めたい場合は、デジタルツール・システムの導入を検討するとよいでしょう。
顧客との信頼関係構築
一般的にインサイドセールスは、顧客との信頼関係を構築しにくいと考えられています。これは非対面で営業活動を行うためです。信頼関係の構築は、インサイドセールスで直面しやすい課題といえるでしょう。この点を踏まえて、フォローアップをこまめに行う、見込み客のニーズに先回りして対応するなどの取り組みを行い、信頼を獲得することが大切です。
部署間の連携・フォロー体制
インサイドセールス部門は、原則としてマーケティング部門、営業部門などと連携しながら業務を行います。部門間の連携・フォロー体制が、業務の成否に大きな影響を与えます。したがって、連携やフォローがしやすい体制を構築しておくことが大切です。具体的な取り組みとして、3部門合同のミーティングを定期的に行い、目標や課題を共有するなどが考えられます。
IT業界のインサイドセールスをアウトソーシングできる?
IT業界においても、インサイドセールスは重要な営業手法になりつつあります。自社に十分なノウハウやリソースがない場合は、アウトソーシングを検討するとよいでしょう。 BCC株式会社は、大手IT企業の営業部門やマーケティング部門を対象に、ITアウトソーシング事業を展開しています。これまで50社を超えるIT企業の営業支援を行ってきました。主な特徴は、豊富な経験を活用して開発した独自の教育プログラム「BCC-Lapプログラム」を修了したIT営業人材を提供していることです。各人材は、コミュニケーション能力を重視する弊社の採用基準もクリアしています。80%以上がAWS認定クラウドプラクティショナーなどの資格を保有している点も見逃せません。また、弊社、お客様、派遣スタッフで情報を共有して、不安要素があれば解決案を模索するサポート体制も整えています。 インサイドセールスをはじめとするIT営業をアウトソーシングしたい方は、BCC株式会社にご相談ください。 参照元:BCC株式会社 https://www.e-bcc.co.jp/outsourcing.html
IT業界のインサイドセールスはアウトソーシングがおすすめ
インサイドセールスは、電話やメールなどを活用して行う非対面の営業活動です。効率化を図りやすい、営業範囲を広げやすいなどのメリットがあります。IT業界においても、重要性が高まっているといえるでしょう。ただし、効果的に運用するために、組織づくりなどのノウハウが求められます。自社で対応が難しい場合は、IT営業アウトソーシングに取り組んでいるBCC株式会社にご相談ください。一般的な派遣会社との違い、活動実績などは、以下のページでダウンロードできる資料で解説しています。ご興味をおもちいただいた方は、こちらも参考にしてください。
インサイドセールスが成果を出すための具体施策
インサイドセールスを導入するだけでは成果に結びつくとは限りません。実際に成果を出すためには、戦略的な運用と現場レベルでの工夫が欠かせません。この章では、成果を上げるために実践すべき具体施策を紹介します。
トークスクリプトの整備とABテスト
インサイドセールスにおいて重要な武器となるのが「トークスクリプト」です。見込み客との初回接触時に、どのような言葉で切り出すか、どのようにニーズを引き出すかが成約率に大きく影響します。
スクリプトは一度作って終わりではなく、常にブラッシュアップを重ねる必要があります。特に有効なのが「ABテスト(比較検証)」です。例えば、同じ内容を異なる導入トークで始めてみる、クロージングの表現を変えてみるなど、小さな差異の効果をデータで確認しながら、最適なパターンを模索していきます。
- A案:「先日、◯◯業界の企業様でお手伝いした事例をご紹介したいのですが…」
- B案:「突然のお電話失礼します、今このお時間3分だけいただけませんか?」
効果測定を行いながら、より反応率が高いスクリプトを全体に展開することで、組織全体の成果を底上げできます。
フォローアップ頻度とタイミングの最適化
一度接触した見込み客に対するフォローアップも重要な施策です。「熱いうちに打つ」ことが鉄則ですが、タイミングを間違えると逆効果になることもあります。業界やターゲットによって最適な間隔は異なるため、自社にとって効果的な頻度を見極める必要があります。
また、フォローアップの内容も重要です。単に「前回のご連絡の件ですが…」といった連絡だけでなく、「最近◯◯のような取り組みが話題になっていますが、お困りごとはございませんか?」など、相手の関心を引く情報提供型のアプローチが有効です。
コンテンツマーケティングとの連動
インサイドセールスとコンテンツマーケティングを連動させることで、相乗効果が生まれます。例えば、ホワイトペーパーやeBookをダウンロードしたリードに対して、インサイドセールスがタイムリーにコンタクトを取ることで、高いコンバージョンが期待できます。
この連携を可能にするためには、マーケティング部門との密な情報共有が欠かせません。MA(マーケティングオートメーション)ツールなどを活用し、コンテンツ閲覧履歴や行動ログに基づくスコアリングを行うことで、より精度の高いアプローチが可能になります。
インサイドセールスの導入ステップと体制構築
インサイドセールスの成果を最大化するには、導入前から戦略的に設計を行い、段階的に体制を整えることが重要です。この章では、導入ステップと、効果的な体制構築のポイントを紹介します。
導入準備フェーズ(業務フロー整理・KPI設計)
導入前の準備段階では、まず「どの業務をインサイドセールスに任せるか」を明確にし、営業プロセスの中での役割分担を定義します。そのうえで、インサイドセールスの評価指標(KPI)を設計しておくことが不可欠です。
例:インサイドセールスに適した業務
- ホワイトペーパーDL者への初回アプローチ
- セミナー参加者へのフォローアップ
- 資料請求後のヒアリング
業務の切り出しが曖昧なまま導入してしまうと、現場が混乱し成果が見えにくくなります。また、評価基準となるKPIも明確にすることで、施策のPDCAがまわしやすくなります。
メンバー構成と役割(SDR / ISR の使い分け)
インサイドセールスには、大きく分けて2つの役割があります:
- SDR(Sales Development Representative): 見込み客の発掘やアポ獲得に特化
- ISR(Inside Sales Representative): より商談化に近い見込み客との関係構築とクロージング支援
導入初期段階では、まずSDR機能に絞ってスタートし、業務が安定してからISR機能を追加するケースが一般的です。役割の違いを明確にし、それぞれに最適な人材をアサインすることが成果を上げる鍵となります。
導入初期に注意すべき落とし穴
導入時によくある失敗例として以下のようなものがあります:
- KPI設計が現実と乖離している: 現場で達成困難な目標設定がモチベーション低下に繋がる
- マーケティングと連携せず孤立運用: 質の低いリードばかりが渡され成果が出ない
- マネージャー不在で場当たり運用: メンバーごとの活動がバラバラになり、ノウハウが蓄積されない
これらを防ぐためには、導入前から綿密な設計とマネジメント体制の整備が求められます。インサイドセールスを「立ち上げプロジェクト」として位置づけ、段階的に体制を構築していくことが成功への近道です。
成功事例と失敗事例から学ぶ運用ポイント
インサイドセールスの導入・運用では、成功と失敗の分かれ目がはっきりしています。ここでは、実際の企業事例をもとに、どのような工夫や落とし穴があったのかを紹介します。これから導入を考えている方は、自社に当てはめて考えるヒントになるでしょう。
成功事例:業務フローとKPIを分解し改善した中堅IT企業
ある中堅IT企業では、インサイドセールスを導入した当初、アポ獲得率が思うように伸びず苦戦していました。原因を調査したところ、マーケティング部門から渡されるリードの質と、インサイドセールスのアプローチ方法にズレがあることが判明。
同社では、マーケ部門とインサイドセールス部門のメンバーが共同でリード評価基準を見直し、KPIも「アポ獲得数」から「有効会話数」「ヒアリング完了率」へと細分化。さらにスクリプトや対応フローを改善したことで、3ヶ月後にはアポ獲得率が2倍に向上しました。
失敗事例:目的不明瞭な導入で形骸化した大手企業
一方で、大手企業A社では、働き方改革の一環としてインサイドセールス部門を新設。しかし、具体的なKPIが設けられず、担当者によって業務内容がバラバラに。最終的には、アウトバウンドコールだけを漫然と行う部隊となり、成果が出せず1年で縮小されました。
この失敗事例から学べるのは、「導入の目的」「達成すべき目標」「連携体制」の3点を明確にしないままスタートすることのリスクです。特に大企業ほど、役割分担が曖昧になりやすいため、戦略的な設計が不可欠です。
成功企業に共通する3つの特徴
- 明確な役割設計とKPI運用
- マーケ・営業との定期的なフィードバック体制
- 現場主導での改善と学習文化の醸成
単にツールや人材を配置するだけでなく、社内全体で成果を育てる土壌づくりが成功の鍵であることが分かります。
インサイドセールスと他部署の協業戦略
インサイドセールスの真価は、単独の部署では発揮されません。マーケティング、フィールドセールス、カスタマーサクセス、さらにはプロダクト部門との連携が、全体最適化を進める上で重要なポイントとなります。
マーケティング部門との連携
最も重要なのは、リードの質と量をコントロールするマーケティング部門との連携です。共有すべきポイントには以下のようなものがあります:
- ターゲット属性とペルソナの共通理解
- コンテンツの閲覧履歴などの行動データ
- ナーチャリング設計とスコアリング基準
たとえば、「特定のホワイトペーパーをダウンロードしたユーザーは、2週間以内にアプローチする」といったルールを設けることで、営業タイミングの最適化が可能になります。
カスタマーサクセス(CS)との連携
成約後のフォローを担うカスタマーサクセスとも、密な連携が必要です。CSからフィードバックされた「受注後によくある質問」「定着に失敗した理由」などは、インサイドセールスのアプローチ改善に大きく貢献します。
また、導入事例をCSが収集し、それを営業資料として活用することで、説得力のある営業トークが可能になります。
セールスイネーブルメントとの連携
セールスイネーブルメントは、営業組織全体の能力を高める活動を指します。インサイドセールスのパフォーマンスを可視化し、定期的にトレーニングやフィードバックを行うことで、組織としての営業力が底上げされます。
部門間のサイロ化を防ぐには、ツール(CRMやチャット)だけでなく、「週次合同会議」や「クロス部門のKPI共有」など、仕組みとして協業を強制的に生む設計が求められます。
インサイドセールス人材に求められるスキルと育成方法
インサイドセールスを成功に導くには、適切な人材の確保と、継続的な育成体制が不可欠です。営業に特化した役割である一方、マーケティング的な視点やITツールの活用力も求められるため、幅広いスキルセットが必要とされます。この章では、インサイドセールスに適した人材像と、育成のための具体的アプローチについて解説します。
求められる基本スキルと特性
インサイドセールス担当者には、以下のようなスキルや特性が特に重要視されます:
- コミュニケーション能力:短時間で信頼関係を築き、相手の課題を引き出す力
- ヒアリング力・共感力:相手の話を的確に把握し、課題に共感したうえで提案を行う力
- 論理的思考力:課題と解決策の関係を筋道立てて整理し、納得感ある提案に結びつける力
- 仮説構築力:相手の状況を推察し、効果的な質問や提案の流れを構築できる力
- ITリテラシー:CRM、SFA、MAツールなどの活用に抵抗がないこと
加えて、チームで連携しながら目標を追いかけられる協調性や、自走して改善を続けられるセルフマネジメント力も不可欠です。
適性の見極めと採用基準
インサイドセールスでは「トーク力がある=成果が出る」とは限りません。むしろ、相手の話に耳を傾け、丁寧に対応する姿勢を持つ人材が成果を出す傾向にあります。
採用にあたっては、以下のような観点から適性を判断するとよいでしょう:
- 電話・Web面接時の傾聴姿勢とテンポ感
- 質問力とフィードバックに対する受け止め方
- PC操作・クラウドツールの理解度(実技テストも有効)
また、未経験者でも成長可能性が高い人材であれば、研修やサポート体制を整えることで戦力化が期待できます。
育成方法とOJTのポイント
インサイドセールスの育成においては、机上の研修と現場でのOJTをバランスよく組み合わせることが重要です。以下のようなステップで段階的にスキルを定着させるのが効果的です:
- 業務理解(営業プロセス、ペルソナ、KPIの理解)
- スクリプト練習とロールプレイ
- 録音レビューによる自己分析とフィードバック
- 実際の業務を通じた改善と成功体験の積み重ね
特に効果的なのが、「うまくいった通話例」や「失敗から学べる事例」をチームで共有する文化の醸成です。属人化を防ぎ、ナレッジを組織に蓄積していくことが、中長期的な組織力強化につながります。
外部パートナーを活用した育成の選択肢
社内にノウハウが蓄積されていない場合は、インサイドセールスに特化した外部研修やアウトソーシングを活用するのも一つの方法です。たとえば、実績あるパートナー企業の教育プログラムを導入すれば、初期フェーズでの立ち上げスピードが格段に上がります。
将来的には社内人材の自走を目指しつつ、外部のプロ人材をメンター役として活用する「ハイブリッド型」の体制も効果的です。
インサイドセールス人材の育成は、短期間で完結するものではありません。しかし、適切な育成方針と継続的なフォローを行うことで、組織にとって大きな資産となる人材が育っていきます。
インサイドセールスはやめとけと言われる理由とは
「インサイドセールス やめとけ」と検索される背景には、仕事の意味がわかりにくいと感じる人が一定数いることが挙げられます。商談を直接クロージングしない役割の場合、成果が数字として見えづらく、やりがいを感じにくいケースもあります。
また、企業によっては業務がテンプレート化されすぎており、単調な架電やメール対応が中心になることも否定できません。一方で、体系的に学べる本や、最新事例を共有するカンファレンスも増えており、正しい環境を選べば成長性の高い職種です。
「やめとけ」という評価は、仕事内容や企業理解が不足したまま求人を選んだ結果である場合も多く、職種そのものに問題があるとは限らない点も理解しておく必要があります。
インサイドセールスに向いてる人の特徴とは
インサイドセールスに向いてる人の特徴は、「対話を設計できる人」です。単に話すのが得意というより、顧客の課題を整理し、情報をわかりやすく伝えられる論理性が求められます。
トークスクリプトやメール文面などのテンプレートを活用しながら、自分なりに改善できる人は特に適性が高いでしょう。また、職種の意味や役割を理解し、マーケティングやフィールドセールスとの連携を楽しめる人も向いています。
最近では専門書籍や業界カンファレンスを通じて学習機会も増えており、成長意欲のある人にとっては魅力的な求人が多い職種です。
インサイドセールスのフルリモートは可能なのか
インサイドセールスは、営業職の中でもフルリモートと相性が良い仕事です。オンライン商談ツールやCRMの普及により、場所に縛られず成果を出せる環境が整っています。
ただし、業務が属人化しないよう、トーク内容や対応フローをテンプレート化し、チーム全体で共有する仕組みが重要です。フルリモートの意味を正しく理解せず、孤独になってしまうケースもあるため、教育体制やナレッジ共有の有無は求人選びの重要な判断軸となります。
最近では、リモート営業をテーマにした本やオンラインカンファレンスも増え、学びやすい環境が整いつつあります。
インサイドセールスの役割拡大と今後の展望
インサイドセールスは、従来の「電話営業」や「テレアポ」の枠を超え、ビジネスのあらゆるプロセスに関与する戦略的な存在へと変化を遂げつつあります。特に、日本国内のIT業界では、社内の営業体制の見直しや分業の最適化が進み、インサイドセールスに求められる役割は拡大しています。
社内体制と分業による効率向上
従来の訪問営業に頼った営業スタイルから脱却し、社内の体制を分業型に整備することで、営業活動の効率は大幅に向上します。例えば、リードの獲得をマーケティング部門が担い、リード育成からアポイント獲得まではインサイドセールスが担うといった分業体制を採用する企業が増えています。
このような体制は、セールスプロセスの明確化にもつながり、社内連携や情報共有の促進、リードの成約率向上を実現します。
データドリブンな営業戦略の必要性
近年では、営業現場における「勘」や「経験」から脱却し、データに基づいた意思決定が求められるようになっています。たとえば、アポイント獲得率や商談化率、クロージング率などの各指標を定量的に分析し、どのタイミングでどのようなアクションが有効かを判断することが不可欠です。
このような分析に基づいた営業プロセスは、sales活動の属人化を防ぎ、社内のナレッジとして蓄積されていきます。
リード獲得から成約までを担う「戦略型インサイドセールス」へ
従来のようなテレアポ中心の役割から、データやコンテンツを活用してリードの状況を見極め、商談に最適なタイミングで提案する「戦略型インサイドセールス」への転換が進んでいます。
たとえば、オンラインセミナー(ウェビナー)やホワイトペーパーなどのコンテンツを活用してリードを育成し、購買意欲が高まった段階でクロージングに向けたアクションを起こすといったプロセスが一般的になりつつあります。
このような取り組みは、イベントやセミナーなどで得られる顧客データをもとに、状況に応じた最適な提案が可能となり、成約率の向上にもつながります。
現場と経営をつなぐインサイドセールスの可能性
インサイドセールスは、ただの「営業の前工程」ではなく、ビジネス全体を俯瞰するポジションとしても注目されています。特に、新規開拓だけでなく、既存顧客へのアップセルやクロスセルにも貢献できる存在として、経営層からの期待も高まっています。
その役割は、単なるアポイント取得にとどまらず、社内での情報収集、競合分析、コンテンツ作成、営業資料の整備、さらにはセールスチームへの知識共有にまで及びます。
教育・育成体制の整備と外部リソースの活用
インサイドセールスに求められる知識やスキルは多岐にわたるため、社内での教育体制の整備が重要です。一方、すぐに体制を整えるのが難しい場合は、外部の研修や無料のe-learning、アウトソーシングサービスなどを活用するのも有効です。
最近では、日本全国でセールス支援に特化したサービスが増えており、状況に応じて柔軟にリソースを確保することが可能になっています。
今後の展望とキーワード
インサイドセールスは今後、さらに多くの企業で導入が進み、「データとコンテンツを活用し、適切なタイミングで最適な提案を行う存在」として、営業戦略の中心的な役割を担うことが期待されています。
そのためには、セールス部門だけでなくマーケティングやカスタマーサクセスと密接に連携し、「明確な目的のもとでのプロセス設計」「チーム間での役割分担」「社内全体の成果を意識した指標設計」が不可欠です。
今まさに、インサイドセールスはその「立ち位置」や「担う役割」を再定義されている最中にあります。目次に掲載されるべき重要な要素として、これからも注目しておくべき領域といえるでしょう。